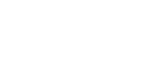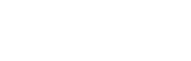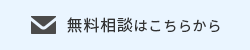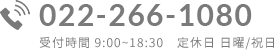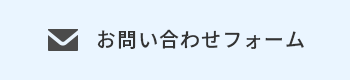【売却事例vol.3】相続登記未了の不動産売却と手続き事例|仙台市青葉区 2024.12.20
お客様の事例
| 時期 | 令和5年11月に引渡を完了 |
|---|---|
| 所在 | 仙台市青葉区霊屋下 |
| 地積 | 仙台市青葉区霊屋下 |
| 価格 | 4,500万円 |
<概要>
当社管理の駐車場に、隣地から木の枝が張り出して駐車の妨げになり、枯葉が大量に落ちるなどしていたため、隣地に所有者本人が居住している様子がなかったことから、町内会を通じて管理者(相続人)に連絡していただき、当方で枝を剪定する了解をいただきました。その後、相続人である兄妹から敷地内の植栽の剪定やゴミ類の撤去などの相談を受け、作業とあわせて土地の利用方法について相談を受けることになりました。
当初は土地をそのまま利用してくれる方を探し地代を得ることができないかという相談でしたが、解決しなければならない課題が多く、投下する資金も高額になることが予想されることから、一定規模の建物が建設可能な状態を想定した場合の土地の価格から、その状態にするための費用を差し引き、さらにリスクを考慮した価格で売却先を探すことになりました。
しかし、土地上に親戚名義の建物があること、継母に相談者以外の相続人いることなど、調査の過程で解決しなければならない課題が増え、相談者からの申し出で、相談者本人が行わなければならない多少の手続きを除き、境界確定測量、道路の狭隘協議、相続登記や建物等の解体工事、相続人対策などは当社が行い、それらに要する費用を差し引いた金額で当社が土地を取得することとして手続きを進め、最終的には当社代表者が個人として土地を取得することになりました。
その後、当社は土地上に共同住宅を建設し、令和6年10月から運用を開始しました。
土地:
・市街地中心部に近く利便性の良い住宅地にあるも、前面道路(市道)の幅員が後退未了のため十分ではない
・道路と宅地の間に最大2mほどの段差がある
・隣地との間にも段差がある
・間口に対して奥行距離が2倍を超え40m以上ある
・20年以上前に実父が死亡している(1次相続)が、相続登記を行っていない
・半年前に継母が死亡して2次相続が発生した。継母には前夫との間に子供があり、相談者2人以外に相続人が2人いる
・土地上に複数の古家があり、実家の建物と貸家として使っていた建物以外に、親戚が所有する建物もある。その建物の所有者にも相続が発生しているが相続登記がなされていない
・古家の一部を借家人が占有している
・境界が確認できない箇所がある
<ご相談内容と課題の整理>
最初に持ち掛けられた相談は、過大な投資を行わずに当地で事業をする人を探したい、すなわち貸地として賃料を得たいという内容でした。
しかし、以下のような課題が山積していることがわかりました。
➀土地と道路との間に最大2mの段差がある
②道路の幅員は実質3m程度しかないため、段差もあることから重機や廃材を搬出するための車両の乗入れができず、解体工事には通常の何倍もの手間・費用を要することが容易に予想される
③相続に関する手続きができておらず、特に継母とその前夫との間に生まれた相続人とは面識すらないため、遺産の分割協議の出口が見えない
④土地上には相続登記未了の遠方に居住していた親戚名義の建物があり、相続人の了解が得られなければ建物を解体することもできない
➄建物以外に大きな木が鬱蒼と茂り、建物内外に多数の残置物がある
⑥古家の一部を借家人が占有している
⑦建物を建設するためには道路からの後退(セットバック)を行わなければならず、そのためには境界確定測量や狭隘協議も必要
⑧現況の玉石積み擁壁を解体して、後退した位置に擁壁を再構築しなおす必要がある
以上のように、第三者が利用可能な状態にするためには解決すべき課題が多く、事前の投資もかなりの額に及ぶことがわかりました。
<ご提案>



土地を賃貸して地代収入を得る方法はでは、前述の課題を解決するために投下した資金を回収することは困難であり、当初のご要望を叶えることは難しいという判断に至りました。そのため、相談者自身がさらに資金を投下して建物を建てて収益を得るか、売却するかの二択になりました。もちろん、何もせず現状のまま賃貸するという方法もありましたが、前述のとおり放置できない課題が多くあることや、貸主として事前に解決しなければならない課題も多かったので、売却する道を探ることになりました。
さて、売却するためにどこまでの課題を相談者自身が行うかを考えることになりました。第三者に売却するためには、売買契約の締結後に売主が解体工事や確定測量を行うか、買主に任せてその分売買代金を調整するという方法もあります。代金から解体費用や測量費用などを差し引いて売却する場合には、どうしても費用を多めに考えることになり、売主の手元に残る金額が減ることになります。また、地中埋設物や越境などの瑕疵の心配もあり、境界確定協議が長期に及ぶ若しくは不調に終わるというリスクも存在します。そこで、解体工事は当社が管理している隣接地の駐車場から行えば過大な費用を要せず工事が可能であり、結果、相談者が得ることができる代金も過分に減らすことがないことから、第三者への売却は行わずに当社が買主として相談者とともに様々な手続きを行ないながら土地を買い受けることになりました。
<課題の解決>
① 道路との間の段差は、解体工事を行う上での問題はなくなりましたので、買受後に擁壁を構築すれば済みます。解体や擁壁の再構築費用を想定される売買代金から差し引いて取引価格を決めることになりました。
② 道路の幅員の問題も解体工事や建物の新築工事を行う上では、隣地駐車場からのアプローチが可能なため大きな問題にはなりませんでしたが、境界確定測量の結果80cm近く後退(セットバック)することになりました。
③ 継母と前夫との間の相続人(姉妹)の問題は、相談者兄妹と共通する相続財産(抵当権)について、その相続人姉妹が相続放棄の手続をとるとの情報が得られ、相談者を通じて相続放棄申述受理通知書の写しを入手することができました。そのため、相談者兄妹と継母が20年前の実父の財産を相続し、継母の相続はこの相続人姉妹を除く相談者兄妹が2分の1ずつ相続する登記を行いました。
④ 親戚所有の建物は築年月不詳で、とても使用に耐える状態ではありませんでした。そこで、相続人がこの建物を再び利用する予定がないことを確認しつつ、建物の解体に要する費用は請求しないことを条件に、所有権を放棄することと解体後滅失登記に協力する旨の書面の作成に協力いただき、建物の解体と滅失登記を行うことができました。
⑤ 解体はなるべく短期間で完了できるよう段取りし、近隣への迷惑もお掛けしないよう配慮しながら工事を行いました。
⑥ 借家人は入院療養中で、余命いくばくもないこと。占有している建物に戻ることできないことが判明しました。借家人の親族に連絡し、建物を解体する予定であることを告げ、古家内の家財の引き取りをお願いし、親族によって撤去を完了していただきました。
⑦ 境界確定測量と狭隘協議の結果、道路から後退する距離も確定し、後退部分は市に寄付する手続きなども念頭に、合・分筆の登記も行いました。
⑧ 前述の様々な作業と並行して、新築する建物(共同住宅)の配置・規模も確定させ、セットバック部分も含め、道路から6mほど後退した位置に擁壁を構築して駐車場を設け、南側の隣地との間にも擁壁を構築して鉄骨造3階建・12世帯の共同住宅を建設することにしました。
相続人姉妹との連絡や交渉、建物の借家人の親族への連絡などは相談者に任せ、相続登記や解体工事、建物の滅失登記、境界確定測量や狭隘協議等は買主たる当社代表者が費用負担も含めて行う内容で土地の売買契約を締結し、建物の解体が完了した時点で代金決済と引き渡しを完了しました。


<スケジュール>
令和4年
9月 当社管理の駐車場にはみ出している植栽の枝の剪定の了解をいただく
作業完了の連絡したところ、敷地内の植栽剪定・片付けの見積を依頼いただく
10月 敷地内の作業着手時に、相談者から相続登記未了の土地建物について相談を受ける
11月 継母の相続人の存在が判明し、当該相続人への財産分与の割合・額などについて相談
相続登記未了の親戚名義の建物の対応方法などを相談
境界確定測量や解体費用、課題の整理と解決方法など精査し、相談者と協議を続ける
令和5年
3月 継母の相続人が他の財産の相続を放棄したため、当地は相談者二人が相続することに
これに伴う相続登記、建物等の解体工事や境界確定測量など、高額な費用や手間がかかることなどから、当社が土地を買い受ける相談を始める
5月 建物の借家人の親族から家財の撤去に協力いただけることに
6月 親戚名義の建物の相続人の所有権放棄や解体費用免除について相談者と協議
相談者から上記の相続人に対し連絡の上、当社から相続人に書類を送付し所有権放棄に関する確認書を受領
8月 買取りの金額やスケジュール等を提案し、了解をいただく
9月 売買契約を締結
相続登記申請、境界確定測量に着手
10月 実家建物内の家財の整理
建物解体工事に着手
11月 解体工事完了
代金決済・引き渡しを完了
<お客様の声>
親戚や相続人との連絡・交渉が必要だったものの、当社が管理している駐車場を解体工事等のために使うことができたため、代金から差し引かれる費用を最小限に抑えることができ、納得のいく金額で取り引きができたことを大変喜んでいただきました。また、今回の売却は継母の居住用財産の譲渡にあたるため、売買や解体工事など自治体に提出する書類や資料を提供させていただき、被相続人(継母)の居住用財産の売却に係る譲渡所得税の控除も適用できたことも喜んでいただきました。 さらに、周辺に居住している方たちからも、廃屋がたち並んでいた土地が綺麗に整備され、防犯面も美観も格段に改善されたこと、建物は道路から6m以上後退した位置に建てられたため圧迫感がなくなり、道路の幅員も拡幅されたため車の往来がしやすくなったと喜んでいただきました。