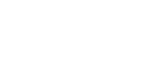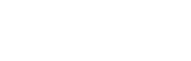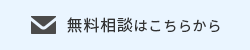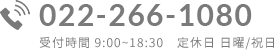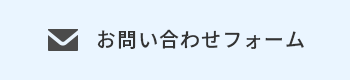「評価額=売値」ではない?相続した土地を高値で売却するための必勝法」 2025.07.30
<この記事を読んでもらいたい方>
●土地を売りたいけれどその価格をどうやって決めればよいのかわからない
●土地の価格には種類があると聞いたけれど、その違いはどこにあるのか
●なるべく高く土地を売るためにできることを知りたい
土地の売却は不動産会社の方でない限り、ほとんどの方は初めての経験でしょう。
売却初心者にとって、どういった価格設定をすればよいのかわからないのは当たり前です。
ただこの価格設定によって売買の動向が決まるといっても過言ではないほど重要な点であるのは確かです。
では、その価格の決め方や参考となる指標、また高く売るポイントなどについて紹介します。
<この記事でわかること>
●土地の価格である評価額と売値の違い
●売値とはどういった価格で、どのように決めればよいのか
●なるべく高く売るためにおさえておくべきポイント
1.土地の評価額と売値の違いとは?

土地を売却する際は価格を設定して売り出しますが、このとき評価額と売値との違いに関連する正しい知識を身に付けることで、理想的な売買取引を実現できます。
では土地の評価額と売値との違いはどこにあるのでしょうか。
土地の評価額とは?
土地の評価額は、国などの公的な機関が一定の基準に沿って決めた価格で、相続税や固定資産税などおもに税金を決定するための指標となる価格です。
その土地の価値を、使用目的や面積・状態、また立地など様々な条件と照らし合わせて考慮・決定され、金額として表されます。
土地の売値とは?
売値は第三者によって決められる価額ではなく、売主の判断によって自由に決められる販売価格です。
資産の状態、市場の相場や需要などで常に変動し、市街地や人気エリアあたりでは評価額よりも高額になることが一般的です。
両者の違い?
評価額は国や都道府県が公的に調査し設定した価格です。
これに対し売値はあくまでも売主の個人的な希望額です。その評価を相当とみなすか、みなさないかは、買主が決めます。従って、売主が設定した価格で即売買が成立するというわけではありません。そのため重要となるのが、不動産業者など専門家による価格の査定と助言です。
2.土地評価額の分類

ひと口に評価額といっても、実際には様々な種類があり、それぞれの違いを知っておくとよいでしょう。
おもな評価額は以下の5つです。
- 実勢価格
- 公示価格
- 基準地価
- 相続税評価額
- 固定資産税評価額
実勢価格
まずは実勢価格からみていきますが、これは実際に不動産の取引がおこなわれたときの、具体的な数値を指します。
実勢価格は市場のニーズに影響を受けやすいため、市場価格に近い価格になり、不動産の売却時に価格設定の参考とする方も多い指標です。
ただ、不動産の価格は市場ニーズのみで決まるものではなく、立地やそのときの社会情勢、売却のタイミングなどで変化するため、あくまでも参考としてとらえてください。
公示価格
公示価格とは、地価公示法によって国が決める毎年1月1日時点の標準地の価格で、毎年その価格が更新されます。
毎年同じ場所での価格が公表されるため、地価の変動がわかりやすいのが特徴で、売買価格の他に資産評価額の目安にも使われる数値です。
また公示価格には、国土交通省が発表する公示地価と都道府県による基準地価の2つがあり、双方を照らし合わせて参考にすることをおすすめします。
基準地価
基準地価は都道府県が公表している毎年7月1日時点の基準地の価格で、全国に約2万地点の基準地があります。
公示価格とほぼ同じ評価方法であるため、公示価格の補完的な役割として利用してください。
相続税評価額
相続税評価額は財産を相続する際、相続税を算出するその基準となる価格をいい、財産ごとに計算方法が異なります。
土地の評価方法には2種類あり、1つめが路線価方式で国税庁のホームページにある相続税路線価をもとに算出するものです。
2つめは倍率方式で、こちらは毎年市区町村から送られてくる固定資産税課税明細書にある固定資産税評価額に、その土地に定められた倍率をかけて求めるものです。
固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、固定資産税の計算に用いるもので、3年に1度の見直しがおこなわれ、そのたびに税額もかわっていきます。
固定資産税証明書や固定資産課税台帳などの書類から確認可能です。
固定資産税評価額は、毎年1月1日時点でその不動産を所有する人に対して送付される固定資産税の納税通知書に記載されています。この固定資産評価額や税額、所有者の住所氏名などは、自治体が管理する固定資産税台帳に掲載されており、市税事務所や税務室で縦覧・閲覧が可能です。
ただし、閲覧できるのは、土地や建物などの固定資産の所有者本人、所有者が委任した代理人、同居する家族、借家人、借地人などに限られます。この台帳に掲載されている内容を証明書(台帳記載事項証明書)として交付を受けることができます。
3.土地の売値(市場価格)とは?その計算方法を解説

売値は売主が希望する価格をいい、売主の個人的な希望や理想が含まれる価格です。
ただ相場とかけ離れた額では買い手がつきにくくなるため、価格の調整が必要です。
価格の調整には各評価額を参考にすると求めやすくなります。
以下、各評価額を基に土地の売値を算出する方法をお示ししますが、これらはあくまで参考となる価格ですので、そのまま売値として設定できるものではないことをご理解ください。
実勢価格をもとに計算
実勢価格は実際に取引された土地の価格を示しているため、参考にしやすい指標です。
ただ土地の面積や状況、個人的な事情などの条件が異なるため、そのままの価格を自分の土地に当てはめてはいけませんが、参考にする土地の実勢価格÷参考にする土地の面積×所有する土地の面積の式で求めてください。
例えば、参考にする土地の実勢価格が3,000万円、面積が300㎡、 所有する土地の面積が150㎡の場合は、1,500万円程度が売値を設定する際の参考価格となります。
このような計算方法は、実際に土地の売買取引に成功した方の事例としてよくみられます。
公示価格をもとに計算
公示価格は国土交通省が提供している不動産情報ライブラリーで掲載されているので、所有する土地の近隣を検索してご確認してください。
わからない場合は所有する土地に近い土地の価格を参考にしましょう。
計算式は、公示価格×所有する土地の面積×1.1です。
例えば、公示価格が20万円/㎡で、所有する土地の面積が200㎡の場合、売値を設定する際の参考価格は4,400万円と計算できます。
ただ、都心部などでは少しの距離でも地価が大きくかわるケースも少なくはないため、その点は注意が必要です。
固定資産税評価額をもとに計算
固定資産税評価額は固定資産税納付書や固定資産税課税台帳などで調べてください。
納税通知書の場合は添付されている課税明細書の価格の欄、固定資産税台帳は市区町村の役所で申請の上、閲覧、若しくは証明書として交付を受けることができます。
計算式は、固定資産税評価額÷0.7×1.1で、固定資産税評価額が例えば3,000万円の場合、売値を設定する際の参考価格はおおよそ4,700万円です。
相続税路線価をもとに計算
相続税路線価をもとに売値を計算する場合の計算式は、相続税路線価×所有する土地の面積÷0.8×1.1です。
相続税路線価が15万円で、所有する土地の面積が200㎡の場合、売値を設定する際の参考価格はおおよそ4,100万円が売値の目安です。
この場合の1.1の数値は相続税評価額を算出する際に使う評価倍率で、自分の土地の倍率を調べるには国税庁が運営する路線価図・評価倍率表を参考にしてください。
4.評価額と売値のギャップが生まれる理由
土地には売主の意思とは別に公的な評価が付けられており、売買の際はその評価額での取引ができると思われがちです。
しかし実際は、評価額と売値との間にはギャップが生まれます。
ではなぜそのような差が生じるのかその理由を考えてみましょう。
売主と買主双方に個人的な事情がある
評価額は国や都道府県が調査して設定する額で、その目的はおもに税額の決定になります。
また不動産売買を健全にすすめるため、公的な指標として定めておくと、相場の安定にもつながります。
ただ土地の売買は、金銭による機械的な取引だけでなく、売る人、買う人それぞれの思惑が含まれます。
例えば、その地域への地縁があったり、売主に突出した経営能力があったりすれば、評価額に関係なく価格が決まるケースもあります。
また債務超過に陥った企業や、住宅ローンの支払いが難しくなった方などは、多少安くても早めに売って現金に換えたいという思惑もあるでしょう。
他にも相続に伴う遺産の分割のためや会社の決算のために早急な売却を望んでいる場合もあります。
このように評価額と離れた価格での取引は、売却を急いでいるなど個人的な事情が入り込むケースも多く、これが売値とのギャップが生まれる理由の1つです。
不動産会社によって得手不得手がある
不動産会社には得手不得手があり、会社ごとに強みを持っています。
郊外の田園地帯にある不動産会社に、商業地にある物件の売却を依頼しても、買い手は見つかりにくいでしょう。
つまりその会社が持っている顧客の層による得手不得手があり、売りたい土地の性格とこの顧客の層とを合わせる必要があるのです。
売りたい土地と顧客の層が合えば、評価額よりも高い値での取引の可能性も高くなります。
また不動産会社といっても、賃貸物件の仲介をおもな業務としている会社や、管理に重きを置いているところ、土地の売買を専門としているところなど、得意とする業務内容にも違いがあります。
そうした不動産会社の強みを生かして依頼することが、評価額よりも高値で売るためのコツです。
市場や経済の影響が出る
土地の評価額は国や都道府県が公的に定めている標準価格ですが、実際に売値を設定する際には市場や経済の影響を強く受けます。
たとえば、経済が良好なタイミングで売却活動を始めれば都市部や観光地などの需要が高くなるので、売値が評価額を上回る事例も珍しくありません。
一方で、他国の極端な金融緩和政策や紛争、海外投資家による国内不動産の買い占め、自然災害による建材・人材不足などが起こると不動産市場は不安定になります。
常に流動的な市場や経済の影響は、標準価格に反映することが難しく、結果として評価額と売値の乖離につながります。
つまり、標準価格のみを判断軸にするのではなく、市場や経済の変動要因を理解して売却計画を立てることが理想的な売却を成立させるために重要な鍵となるでしょう。
5.土地を高く売るためのポイント

売主は可能な限り高値で売りたいものですが、立地や状態に問題がある場合はスムーズな売却活動が難しくなります。
人気のあるエリアの土地であれば、高値で売れる確率は高くなりますが、そうでないエリアの場合、どうすれば高く売れるのでしょう。
では土地を高く売るためのポイントをいくつかみていきます。
古屋付き土地は更地にする

土地が売れやすい状態は、その上になにも建っていない更地であることがメリットとなることが多いです。
買い手の視点で考えると、更地であれば、そこに自宅を建てたり、駐車場にしたり、賃貸経営をしたりと自由に活用できます。古家やブロック塀、看板の基礎などがあればそのままでは活用方法が制限され、利用するために余分な投資が必要になるため、都合が悪いことも多いです。
近年では空き家を安く購入して自由にリノベーションしたいと考える買主も増えていますが、やはり一概に「空き家にすると売れる」と断言できるわけではありません。
実際多くの場合では、更地の購入、若しくは購入後に更地化して建物を建築することになります。
古家付きの土地を更地にするためには解体費用が発生しますし、これらの建築物や残置物の撤去にかかった費用は、住宅ローンの対象に充てることができません。
そこにマイホームを建てたい方には条件の悪い土地となり、買い手がつきにくくなるでしょう。価格から解体費用を差し引いた売値で販売し、購入後自分で解体してくださいという売り方では、購入希望者が見つかりにくくなる可能性もあります。
ただ売主の立場で考えると、住宅が建っている土地は、固定資産税・都市計画税の軽減措置が適用されるため、税負担の観点で考えると、更地にしないのも手の1つです。
更地にすると軽減措置が適用されなくなってしまうので、建物解体後の販売期間が長期に及んでしまうと、次年度からの税負担がかなり増えるリスクが生じます。
結果、売買を完遂するためには値下げすることになり、最終的な利益が減る可能性もあるので、慎重な判断が求められます。
売る時期にも旬がある

土地の売買は需要と供給のバランスや景況などに左右されるもので、言い換えれば値上がり基調のときが売却にとって旬の時期です。
どれほど優れた営業担当者であっても、値下がり基調のときに高く売るのは至難の業でしょう。
公示価格などを参考にして値上がり基調の時期に狙いを絞って売り出すのが高く売るためのポイントの1つです。
値引き交渉を前提とした価格設定をする
売主はなるべく高く売りたいのが本音で、逆に買い手はなるべく安く買いたいと思っています。
そのため売買取引ではほとんどの場合、価格交渉、つまり値引きがおこなわれ、売り手が希望する価格よりも安くなってしまいます。
東日本不動産流通機構による調査では、成約価格は平均で売値の87.5%となっており、これを踏まえて値をつけると希望する価格に近い成約価格になるでしょう。ただし、あまりにも高い価格で売りに出しても見向きもされないというリスクがあることを理解しておいてください。
複数の不動産会社から慎重に選ぶ

土地の売値を決める際には、評価額を踏まえて不動産会社が「査定額」を提示しますが、ここで提示される査定額は不動産会社ごとに異なります。これは、各不動産会社が独自に持つ過去の取引実績の情報、市場調査、売却活動のノウハウ、買主の顧客情報などによって基準が変わってくるからです。
たとえば、田舎で立地が悪いけど広い土地をほしがっている買主の顧客リストを持っている不動産会社であれば、条件の悪い土地でも高額取引が期待できます。
一方で、一般的には敬遠されがちな再開発区域の取引実績を豊富に持つ不動産会社であれば、相場以上の金額で取引できる可能性があります。
また、始めから1社のみに査定依頼をすると所有してる土地の相場感をつかみづらいので、安く売ってしまう原因になりかねません。
簡単な情報を入力して複数の不動産会社に査定してもらえる「一括サイト」を利用すれば、簡単にまとめて査定結果を提示してもらえます。気軽に使える便利なサービスですが、簡易査定になるので提示された査定額の根拠が不透明になることが多いです。
少し手間にはなるものの、最低でも2〜3社信頼できそうな不動産会社を見つけて訪問査定をしてもらうことで納得のいく売却が実現しやすくなります。
所有している土地を分筆して売却する
広い土地は、そのまま売ろうとしても購入希望者が見つかりにくいので、用途やニーズにあわせて分筆(土地を分けて売る手段)を検討しても良いでしょう。
一般的な戸建住宅用の土地の面積は60坪くらいまでが多く、これを超える土地は、購入時の総額が高額になることはもちろん、管理の負担や使いづらさを理由に売りにくい場合が多くあります。
よって、広い土地は評価額に対して売値を下げざるを得ない場合も珍しくありません。しかし、分筆で複数に分けて土地を販売することで、それぞれの購入希望者がみつかれば、最終的な売却価格が高くなることがあります。
注意点として、宅地建物取引業の免許を持っていない一般の人が、複数の土地を連続して販売することはできず、これを行うと宅地建物取引業法違反になります。そのため、分筆して土地を売却しようと考えているのであれば、宅地建物取引業者に代理を依頼するか、数年単位の時間をかけて売却する必要があるので、やや手間がかかります。なお、後者は時間をかけたとしても、業法に抵触する可能性もありますのであまりおすすめできません。

土地がどのように利用されてきたか把握する
所有している土地が過去に「どのように利用されてきたのか」を事前に調査しておくことで、地中埋設物の有無、土壌汚染のリスクを知ることができます。ここでいう地中埋設物とは、建物の躯体部分の一部やコンクリート片、建築資材、古い水道管、浄化槽、井戸など、地中に埋まってる廃棄物のことです。
昔は産業廃棄物の処理に関する規制が緩かったため、先祖代々引き継いでいる土地には、基礎工事の阻害要因となる廃棄物が埋まったままになっていることがあります。取引成立後に地中埋設物や土壌汚染が発覚した場合、契約不適合責任を問われて、損害賠償請求や契約の解除につながるおそれがあるので注意が必要です。
古い土地にはさまざまなリスクがあることを知っている買主からは、売買取引を避けられる可能性もあるので、事前に地中埋設物調査をするのもおすすめです。第三者機関の調査で土地に問題がないと証明できれば、敬遠されることなく高額取引につながる可能性が高くなります。
土地の境界線を明確にする
原則として、土地の売主は所有地と隣地の境界線をはっきりとさせる義務があります。これを「境界明示義務」といい、一般的な売買契約においては契約書にその旨条項が設けられています。この義務を全うせずに売買取引すると損害賠償が発生するおそれがあります。
なお、買主が「土地の境界線を確定させていなくても良い」と申し出があった場合に限っては、境界線が曖昧なままでも売買取引が可能です。
しかし、境界線がはっきりしていない土地は、住宅ローンが利用できない、建築時に隣地の所有者とトラブルになる、などのリスクがあるので敬遠されることが多いです。
境界線を適当に設定することはできませんので、境界を確定させるためには、必ず土地家屋調査士などの資格保有者とともに、隣地の所有者に立ち会いを求めて確定作業をおこないます。その後、調査士の押印付き「境界確定図」が作成されるので、不動産会社に提出することで、問題のない土地として通常どおりの売却活動に移ることができます。
もちろんこれら全ての作業を含めて不動産会社に依頼することも可能です。
隣地の所有者の協力が得られなければ土地の境界線を確定できないので、トラブルリスクのある土地として値下げをせざるを得ない可能性もあるので理解しておきましょう。
土地の売買取引で売値を設定する際の注意点
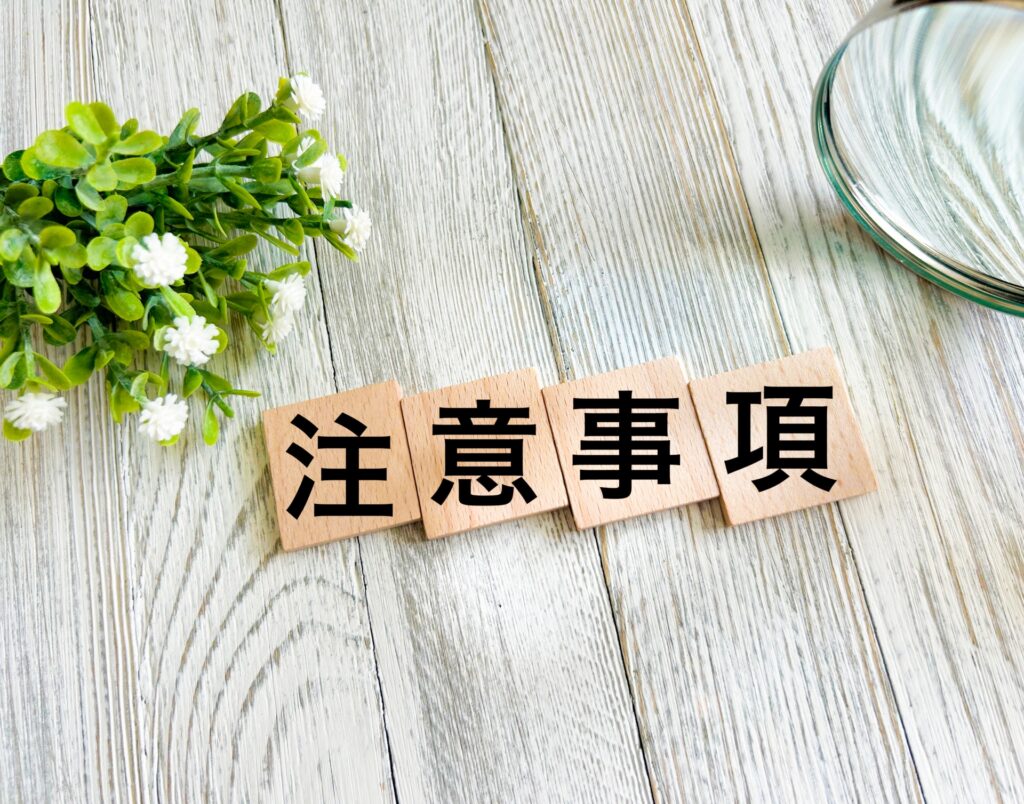
さまざまなデータから算出された評価額や不動産会社の基準で算出された査定額をそのまま売値にすれば良いわけではありません。
売主としては「高く売りたい」と考えるのが当然ですが、売れ残っては元も子もないので適正価格を設定することが大切です。
では、土地の売買取引で売値を設定する際の注意点をみていきましょう。
売却期限を設定する
高額取引を目指して売値を設定した結果、売れ残ってしまっては意味がありませんので、計画的に売却活動をおこなうための期限設定が欠かせません。売却期限を設定しておくことで、不動産会社や購入希望者とのやりとりにもメリハリが生まれて、価格交渉にも前向きに応じる姿勢を持ちやすくなります。
一般的には3か月以内で売却できる金額を「適正価格」と呼び、成約を目指しますが、売却に時間がかかっても良い場合は、適正価格以上の売値を設定しても良いかもしれません。
住み替えを検討している、相続税の納付期間が迫っているなどの理由で3か月以内に現金化を目指すのであれば、適正価格、若しくはやや安価な価格を設定することをおすすめします。
ただし売値を安くしすぎると資金繰りがうまくいかなくなるなどの問題も生じますので、手元に残したい金額と売却費用(売却活動にかかる必要経費)を明確にして、値下げを検討しましょう。
最低取引価格を決める

一般的な売買取引では、売主が設定した売値よりも成約に至る取引金額が低くなることも多々あります。購入希望者から値下げ交渉を持ちかけられる前提で「この価格以下では売らない」と最低取引価格の基準を決めておくことで、あとから後悔するリスクを軽減できます。
売主は「できる限り高く売りたい」と考えるのと同様に、買主は「できる限りやすく買いたい」と考えるので、ダメ元で値下げ交渉を持ちかけるケースもあります。売買取引における値下げ交渉の幅は、5〜10%程度が多いようです。
評価額や査定額よりも売値を安く設定して売却活動をおこなっているのであれば、そこから5〜10%の値下げに応じると手残りするが大幅に減ってしまいます。
一方で評価額や査定額よりも売値を高く設定して売却活動をおこなっているのであれば、そこから5〜10%の値下げをしても適正価格で取引できる可能性もあります。
このように一概に購入希望者の値下げ交渉が適切であるとは判断できないので、事前に最低取引価格を設定しておくことで判断軸をブラさずに済むでしょう。
土地標準価格を基準とする

土地標準価格を基準に売値を設定することで、適正価格から大幅にズレることがなくなるので理想的な成約につながりやすくなります。
国土交通省が発表する公示地価と都道府県による基準地価などがありますが、これらの数字は客観的なデータをもとに不動産取引の適正な指標として公開されています。
適正価格で売却活動を始めることで、国や各都道府県の提示する数字が根拠となり、購入希望者からの理解が得やすくなります。とくに基準地価は、各都道府県が独自調査した結果を公表しているので、より地域密着型の価格設定が可能です。
不動産会社の提示する査定額が公示地価や基準地価から大幅に外れているのであれば、根拠を示してもらうか、客観的データと比較して売値を設定するようにしましょう。
買取業者への売却も視野に入れておく
土地の売買取引では、不動産会社と媒介契約を締結して第三者の購入希望者を探す他、専門の買取業者と直接取引する方法もあります。買取は、不動産会社が家を建てたりリフォームしたりして再販する目的で土地の売買取引がおこなわれます。
一般的な媒介取引の相場よりも安い価格で取引することになりますが、一定要件を満たしていれば早期売却が可能です。所有している土地の立地や形状に問題があり、適正価格以下の売値を設定しても購入希望者がみつかりそうになければ、買取業者のサービスを利用することも検討しましょう。
6.まとめ:納得のいく売却のために
土地を売却するときは、評価額と売値の2つの価格がある点に注意が必要です。
評価額は国や都道府県が評価した価格で、売値は売主が自由に設定できる価格をいいます。
評価額と売値が同じ価格になるケースはほぼなく、売主や買主の個人的な事情や不動産会社の得手不得手などが違いが出る理由となります。
また更地にする、値上がり基調のときに売るなどのポイントを押さえると、高く売れる可能性が高まるため、時間的・経済的に余裕がある方は試してください。
士業の付き合いもあり相談は無料のため、土地の売却でお困りの方はぜひ弊社Arouse(アラウズ)にお任せください。

吉田 健一(有限会社アラウズ 代表取締役)
プロフィール
宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/
相続支援コンサルタント(日管協)/不動産キャリアパーソン(全宅連)
宅地建物取引業者・賃貸住宅管理業者である有限会社アラウズの代表取締役として長年の経験を生かして土地建物の利活用の提案、
売買や賃貸住宅等の管理業務などに幅広く対応し、相続の生前対策や財産分与・処分などについて提携税理士や法律家とともに多くの相談を受けている。
また、公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会の業務執行理事を務める。